



目次
サラリーマンやOLでも年間10万円以上節税することはできる!
収入や支出、家族構成など様々な部分が影響しますが、サラリーマンでも年間10〜20万円の節税効果を実感することはできます。
でもほとんどのサラリーマンやOLさんが自分にどこまでできるのかを理解していないので、認められている節税対策を実践できていないことも。
実際にどんなことができるのかというと・・・
サラリーマンの節税対策
- ふるさと納税
- 住宅ローン控除
- 医療費控除
- 生命保険料控除・地震保険料控除
- 扶養控除
- 特定支出控除
- iDeco(イデコ)
- 資産運用(不動産投資・株式投資)の損失の繰越控除
こんなにも多くの節税対策があるのに、もしかしてまだふるさと納税すら行なっていないという事はありませんか?
消費税がついに10%になるので、今からでも節税効果の実感できることがないのか、一度この記事を読んで考えてみてください。
ふるさと納税で得られる節税効果は?
ふるさと納税とは、寄付した金額から2,000円を引いた金額だけ節税効果を実感できる節税対策。
収入による上限金額の設定はありますが、返礼品ももらうことができ所得税や住民税を先払いすることで節税対策を実感できます。
2019年6月1日から返礼品の還元率が3割未満に抑えられましたが、現在でも充実した返礼品がラインナップされていますし、サラリーマンでも気軽にできる節税対策としておすすめ。
-
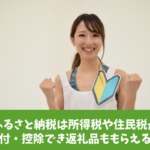
-
ふるさと納税は所得税や住民税が還付・控除でき返礼品がもらえる!
ふるさと納税は所得税や住民税が還付・控除でき返礼品ももらえるお得な制度。まだふるさと納税をしたことがない人は毎年損をしているかも。還元率が下がってもふるさと納税がお得だったり、地域に貢献できる制度なので利用しない理由はありませんよ。
-

-
ふるさと納税の失敗談、初心者がやりがちな損するミスとは?
ふるさと納税の失敗談、初心者がやりがちな損するケアレスミスを紹介します。ふるさと納税をしても税控除を受けられなかったり、必要以上の寄付をしてしまったり、初心者によくある失敗談をまとめて紹介しますので、気をつけてくださいね。
住宅ローン控除で得られる節税効果は?
住宅ローン控除は住宅ローン減税制度とも呼ばれる制度で、マイホームを購入する際に住宅ローンを組んだ人が対象。
住宅ローンの年末残高の1%が10年間、所得税(及び住民税)の額から控除され、最大控除額は10年間で400万円(1年で40万円)になります。
新築住宅以外の中古住宅や増築・リフォームも住宅ローン控除の対象になりますが、細かい規定で対象物件かどうかの判断基準が決められていますので、事前に税務署や不動産会社などに確認しておきましょう。
医療費控除で得られる節税効果は?
医療費控除とは年間の医療費が10万円を超えた人を対象にしており、保険診療以外では自由診療でも対象になる制度。
治療費以外で医療費控除になる項目
- 怪我や病気のための通院費
- 介護老人施設の費用
- 妊婦の定期検診や検査費用
セルフメディケーション税制が医療費控除の特例として追加されていますので、どちらかを選んで申請するようにしてください。
生命保険料控除・地震保険料控除で得られる節税効果は?
生命保険や地震保険など年間にかかる保険料の売りの一定額が所得から恋雨女される制度もあります。
対象の保険
- 一般生命保険料控除
- 介護医療保険料控除
- 個人年金保険料控除
上記3つの保険料で最大控除額は所得税が12万円、住民税が7万円の合計19万円も節税効果が期待できるので、保険料の支払いがある人は対象になっているか確認しておきましょう。
扶養控除で得られる節税効果は?
子供がいる家庭では扶養控除の38万円(1人あたり)を控除しているという人も多いのではないでしょうか。
実は扶養控除は生計を一にしている6親等内の血族および3親等内の婚族が対象なので、同居していない両親でも扶養に入れることは可能です。
しかも70歳以上の場合は控除額がさらに上乗せされますので、節税効果が高まるメリットも。
ただ定期的に送金しているなど本当に扶養していることを証明できる書類等を残しておく必要があるので、何もせずに扶養にいれることは避けましょう。
特定支出控除で得られる節税効果は?
特定支出控除とはサラリーマンやOLさんでも仕事に関係する経費が控除される制度のこと。
自己負担分が給与所得控除の半額以上になった場合にのみ適応できる制度ですが、アパレルショップの店員さんが自社ブランドの服を業務のために購入した場合などに利用できます。
全部で8種類に分類されている項目の合計額なので、自己負担で仕事にかかる費用を多く捻出している人は、対象になっているか調べてみる価値はありますよ。
-

-
サラリーマンでも経費が使える特定支出控除は活用すべきか?
サラリーマンでも経費が使える特定支出控除は活用すべき制度なのか?特定支出控除がどのような節税対策に役立つのかを知ることで、サラリーマンの経費について考えてみたいと思います。給与所得者なら特定支出控除の対象ですのでチェックしておきましょう。
iDeco(イデコ)で得られる節税効果は?
iDeCo(イデコ)とは、個人型確定拠出年金のことで年間の積立金額が全額所得控除の対象となり、所得税・住民税を節税することができます。
60歳まで引き出すことができませんが、運用中の定期預金利息や投資信託運用益も非課税になりますので、節税効果を実感しながら老後資金を作ることができる制度。
掛金も低く長期間に渡って税制優遇されていますが、投資を行うことになるので、相場が大きく下落すれば元本割れのリスクがまったくないわけではありません。
-

-
iDeCo(イデコ)とは?私的年金で老後の不安が解消できる?
iDeCo(イデコ)とはどんな特徴があるのか。私的年金で国民年金の不足を補い老後の不安が解消できるのか?iDeCo(イデコ)のメリット・デメリットも紹介しながらどんなものかを徹底解説。老後生活の不安を解消するためにも活用してくださいね。
-
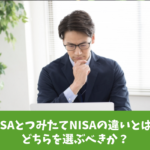
-
NISAとつみたてNISAの違いとは?どちらを選ぶべきか?
NISAとつみたてNISAの違いはどこにあるのか。また実際にNISAとつみたてNISAではどちらを選ぶべきなのかを徹底解説。節税できる投資として国が主体で勧めている少額投資非課税制度のNISAについて紹介しますので参考にしてください。
資産運用(不動産投資・株式投資)の損失の繰越控除で得られる節税効果は?
不動産投資や株式投資などは会社の給与所得に対して、損益通算を行うことができるので、損失が出た際には節税効果を実感できるでしょう。
特に株式投資だと繰越控除も適応され3年間は損失を繰越して所得額から引くことができるので、投資で大きく負けた際にもある程度のリスクヘッジができます。
サラリーマン大家さんが多いのも不動産投資で損失を出して、その損失額を給与所得と相殺して節税効果を実感できるから。
このあたりは専門書を購入すれば具体的な方法が書かれているので、気になる人はさらに詳しく調べてみてください。
サラリーマンの節税の記事まとめ
この記事ではサラリーマンやOLさんでもできる節税対策について紹介してきましたが、全てを全額利用できれば10〜20万円どころか100万円を超えることも。
特に医療費控除は最高額は200万円と非常に高い節税効果が期待できますので、もし本当に高額な医療費を支払った場合には確定申告を絶対に行うべきです。
サラリーマンの節税対策
- ふるさと納税
- 住宅ローン控除
- 医療費控除
- 生命保険料控除・地震保険料控除
- 扶養控除
- 特定支出控除
- iDeco(イデコ)
- 資産運用(不動産投資・株式投資)の損失の繰越控除
他にもクレジットカードで税金を支払って、ポイント還元を受ける方法とか、寡婦控除(寡夫控除)、雑損控除などもありますので状況に応じて調べてみてください。
サラリーマンやOLさんでもしっかり勉強することで、これだけ多くの節税対策が利用できます。
国や市区町村はあえて何が利用できるかということは教えてくれませんので、あなたが主体的に行動することが節税効果を実感するための第一歩ですよ。
-

-
株式投資の基礎知識!メリットやデメリットも知っておこう!
初心者でもわかるように株式投資のメリットやデメリットも紹介しますので、基礎知識を学びませんか。株式投資って難しいイメージがあるかもしれませんが、メリット・デメリットを理解しておけば、初心者でも少額から簡単に始められる身近な投資ですよ。

